ヴィネはすでに1年以上前から、ドアノブや手すりなど消毒や掃除がやりすぎていると警報を鳴らしていました。
消毒については、その根拠が確か長崎大学の研究結果からアルコール消毒が効果ある、とのことで取り入れられたはずですが、研究では50%濃度のアルコールに何分か浸して置いたらウイルスの感染力がなくなったというもので、アルコールスプレーをしてさっと拭くことで殺菌されているかどうかは言及していないのです。もしかすると、単に水拭きだけと変わりはないのかもしれません。
今の日本人の頭の中には「人が手を触れるものには相当の確率でコロナウイルスが付着していて、消毒しなければ感染してしまう」という恐怖が頭の中にこびりついていると思われます。本来は確率で述べなければいけないところ、なんても怖い、あぶない、消毒しろ、掃除しろ、しゃべるな、離れろ、とエスカレートしています。
アメリカCDCがいくつかの論文を根拠に、掃除や消毒に関する見解を出しました。
人が良く触る場所にウイルスがついているかどうか、その場所はどのくらいの頻度で触れられるのかなどを調査。
調べた348か所のうち少しでも新型コロナウイルスが見つかったのは8.3%。横断歩道のボタン、地下鉄駅のドア、レストランのドアなど12か所の対象のうち、一番割合が高かったのはごみ箱の蓋で、25%。それぞれの対象にどれだけの人が触るのかも調査した。触ったものから手、そして口などの粘膜にどれくらいでウイルスが移動するかといったことを加味して解析した結果、対象のものを触って感染するリスクは一千万分の一から1万分の4(中央値は百万分の2.2)と推定。これはインフルやノロと比べても低い数字です。
ヴィネとしてはこれはマスクをつけている場合なのかそうでないのか、のコメントが欲しかったです。マスクをつけていると、口元を手で直接触ることはほとんどなくなりますからね。そのことを考慮に入れた研究なのかどうかは重要なポイントになると思うんですが。
そして(多分、感染者が出ていない場所なら)ボタンやドアノブなど人が良く触るところは一日1回の清掃を勧めている。感染者が出た時は清掃と消毒をしてほしいとしている。
ヴィネ的にもう少しわかりやすく言えば、感染者が出た場所や、そうなりやすいカラオケや酒を飲む場所以外では、コロナの前と同じような掃除でいいのではないか、と思います。一般の会社、物を売るお店や教育現場での過剰な消毒や清掃は確率から言えば、かなり低いのに過剰な対策を取っていると思われます。
コロナへの取り組はあくまで確率の問題で考えるべきなんです
そういう考えがないと、図書館で借りた本を読むのに、手袋付けた手で1ページめくるごとにアルコール消毒しなきゃいけませんよ。

(
11 )

読み込み中...

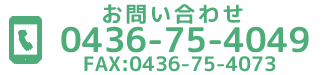

 (13 )
(13 )

